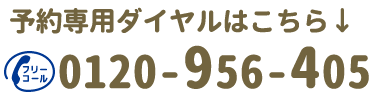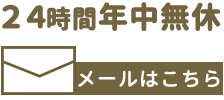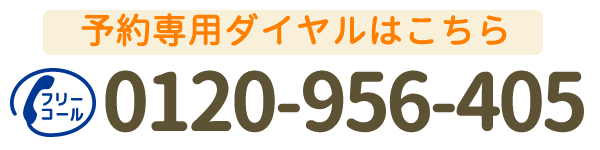◆相続放棄の熟慮期間に関する裁判例◆
相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間を【熟慮期間】といいます。
また、熟慮期間内であれば、期間の延長を申請できます(民法915条1項ただし書)。
熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が、相続の開始の事実(被相続人が死亡したこと)と、これにより自己が相続人になったことを知った時をいいます。
ところが、最高裁判所は、熟慮期間の起算点につき、前記の場合に加え、例外として相続人が、被相続人に相続財産(債務などマイナスの財産を含む)が全く存在しないと信じ、かつ、財産の調査が困難であったなど、そう信じたことについて相当な理由があるときは、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識すべきであった時から起算されるとしました。(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
上記のほか、熟慮期間の起算点の繰下げが問題となった裁判例は次のとおりです。
【起算日の繰下げを認めず、
熟慮期間経過後の相続放棄の申述を却下されたケース】
②相続人が、被相続人死亡後5年あまりが経過してなされた債権者からの返済請求によって、初めて被相続人の保証債務の存在を知ったとしても、被相続人の死亡の時点で被相続人所有の不動産があることを認識している以上、遺産分割協議の結果、遺産を何も取得しなかったとしても、熟慮期間は被相続人死亡時から起算されるとした事例(岐阜家庭裁判所平成11年2月5日審判)
③相続人らが、被相続人死亡直後、相続財産の一部である不動産を長男に単独取得させる旨の合意をし、その他の相続人が相続分不存在証明書に署名押印している以上、当時、負債を含めた相続財産の全容を明確に認識できる状態になっていなかったとしても、熟慮期間は遺産分割の合意をした日から進行するとした事例(東京高等裁判所平成14年1月16日決定)
【起算日の繰下げを認め、
3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められたケース】
⑤相続人は、被相続人死亡の時点で相続財産の存在を知っていたが、自分は被相続人から生前贈与を受けており、相続人間で、二男が跡をとり老婆の面倒をみるとの話し合いがされていたので、その財産は二男が相続し、自分は相続する財産はないと信じたことにつき、そのように信じたとしても無理からぬ事情が認められるとして、3ヶ月経過後の相続放棄を認めた事例(名古屋高等裁判所平成11年3月31日決定)
⑥相続人が、相続開始時に被相続人所有の財産が存在することを知っていたが、遺言により自分は一切相続することはないと信じていたときは、熟慮期間は相続債務の存在を知った時から進行するとした事例(東京高等裁判所平成12年12月7日決定)
最高裁判所の判例は、熟慮期間の起算点繰下げの要件のひとつとして、「相続財産が全くないと信じたこと」を挙げています。
相続財産があることは知ってはいたが、他の相続人がすべて相続するため、自分が取得すべき財産はないと信じた場合をどう考えるかについて、下級審の裁判例が分かれています。
遺産分割の協議をしている場合については、上記②、③の裁判例のように熟慮期間の繰下げを認めないものが主流です。
これに対し、⑥の裁判例のように遺言により相続財産が全部他の相続人のものとなった場合は、相続人の共同相続財産がないことになり、繰下げを認めてもよいケースだと思われます。