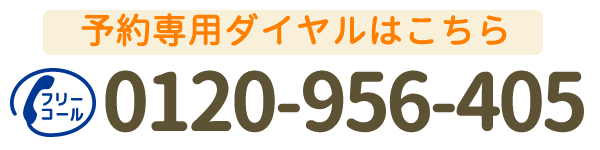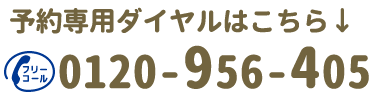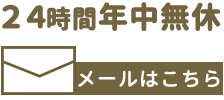◆未成年者の相続放棄◆
■未成年者の相続放棄とは
未成年者が相続放棄をするためには、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立て、その代理人から相続放棄の申述をしなければなりません。
判断能力が未熟な未成年者は単独で相続放棄をすることはできません。
経験の浅い未成年者では、遺産に関する権利関係を正確に把握することができず安易な相続放棄を選択してしまい、それにより不利益を被る恐れがあるからです。
未成年者の利益を保護するためにも日本の法律は未成年者の単独での相続放棄を認めていません。
未成年者が一定の法律行為(売買契約、賃貸借契約、契約解除など)をする場合には、法定代理人である親権者(父・母)がその未成年者に代わって法律行為の意思決定をします。
しかし、相続放棄という行為は、その性質上、法定代理人と未成年者との間で利益が相反するものと認定されているため法定代理人は未成年者を代理して手続きをすることはできません。
そこで、原則として未成年者が相続放棄をするためには、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
利益が相反するとは、対立する当事者の一方が利益を受けると他方に不利益を与えてしまう関係を指します。
相続放棄は、家庭裁判所へ申述をする方式で行います。
相続放棄は、売買契約のような対立する当事者がいるわけではありません。
一見すると相続人間に利益の対立はありません。
しかし、判例の見解をみると相続放棄も利益相反になると判示しています。
なぜ相続放棄が利益相反関係になるのでしょうか。
遺産が預金1000万のみで、その他には借金を含めて存在しません。
このようなケースで、子だけが相続放棄を行い法定代理人は相続放棄をしないとするとどうなるでしょう。
母だけが1000万円を手に入れるというメリットを受け、子は一切利益を受けることができません。
子供の利益を犠牲に、親権者である母が相続財産を独占できてしまうのです。
このような関係でも利益が相反すると判断されています。
この話をすると、
「親が子供の不利益になる行為をするわけがない。」
「特別代理人の選任など必要ない。」
と考えるもしれません。
しかし、法律上、利益相反行為に該当するかどうかは実際に不利益を受けるかどうかは関係ありません。
その行為が外形上、客観的にみて当事者間で利益の対立があるどうかで判断します。
つまり、未成年者の相続放棄により親権者である親が利益を受ける関係にあるのであれば、それだけで利益相反行為になります。
以上のように、未成年者の相続放棄は利益相反行為にあたるため、その未成年者の利益を守るため中立的な立場である特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
そして、選任された特別代理人は未成年者の利益を考え相続放棄をするかどうか判断します。
最後に特別代理人を選任しなければならない具体的なケースをまとめます。
2.法定代理人が相続人ではなくても、その親権に服する未成年者が複数いる場合
■未成年者が相続放棄できる期間
相続人が未成年者又は成年被後見人であるときの相続放棄の熟慮期間は、
「その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったこと知った時から」
起算されます(民法917条)。
■未成年者は、自分だけでは相続放棄ができません。
ただ、親(法定代理人)が自由に子を代理して相続放棄できるとなると、子だけ相続放棄をさせて自分の法定相続分を増やすことが可能となってしまい、子の利益を害する危険性があります。
そこで、未成年の子だけが相続放棄するようなケースの場合、子の利益のために親とは別人の特別代理人を選任する必要があります。
親子一緒に相続放棄するようなケースであればこういった危険はないため、親(法定代理人)からのご依頼のみで相続放棄をすることが可能です。