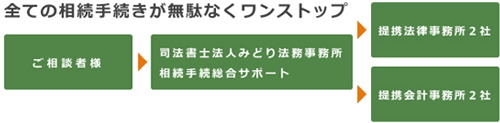遺贈の放棄との違い
遺贈の放棄と相続放棄の違い
【遺贈】とは、被相続人が遺言でする贈与のことです。
被相続人が遺言書に贈与の意思を表すことによって相続財産を第三者に譲ることができます。
遺贈を受ける人を【受遺者】と呼びます。
この受遺者は相続人である必要はありません。
個人である必要もありません。
財産を渡したい相手がいれば、個人、法人を問わず自由に遺贈することができます。
そして、この遺贈は、譲り渡す対象財産によって二種類に分類されています。
【包括遺贈】と【特定遺贈】のふたつです。
【特定遺贈】
特定遺贈とは、特定の相続財産を遺贈することをいいます。
遺言書には「東京都千代田区〇丁目〇番〇ー〇号の土地を山田太郎に遺贈する」という要領で記します。
「生前に息子の嫁に献身的な介護を受け、快適な生活を送ることができた。感謝しても感謝しきれない。
自分が死んだら自己所有の財産を譲りたいが、相続人ではないので相続によって遺産を取得させることはできない。
相続人を無視して全財産を贈与すると、受遺者と相続人との間で争いになることは火を見るよりも明らかだ。」
このようなケースでは特定遺贈を活用するといいでしょう。
【包括遺贈】
包括遺贈とは、相続財産の全部または一定の割合を遺贈することをいいます。
遺言書には「相続財産の2分の1を山田花子に遺贈する」といった要領で書きます。
包括遺贈を受けた者を包括受遺者と呼びます。
特定遺贈と違い、包括受遺者は相続財産に関し大きな利害関係を持ちます。
そのため包括受遺者には次のような規定が置かれています。
-
*******
民法990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する
*******
この条文は包括受遺者を相続人と同一視し、法律上、相続人とみなしなさいという意味です。
そして、ここで注意すべきは、権利「義務」の両側面の拘束を受けてしまうということです。権利だけではなく義務も負担しなければなりません。
特定遺贈とは異なり包括受遺者は被相続人が負っていた負債などのマイナス財産も引き継がなければなりません。
プラス財産のみならずマイナス財産にも気を配る必要があります。それを怠ると思わぬ不利益に見舞われ、人生を狂わされることになるかもしれません。
遺贈の放棄との違い
遺贈は単独行為
通常の【贈与】は契約です。贈与する人と贈与を受ける人の意思の合致が必要です。
一方、同じような効果がある遺贈はどうでしょうか。合意が必要なのでしょうか。
【遺贈】は遺言者が遺言書にその旨を書くだけで有効に成立します。
遺贈をする者と遺贈を受ける者、双方の意思の合致までは要求していません。
遺贈とは遺言者の一方的な意思表示によって、その意思表示の内容どおりの効果を生じさせる単独行為なのです。
しかし、受遺者には遺贈を断る権利が与えられています。
どんなに利益になる行為だとしても受遺者に遺贈を受けることを強制するわけにはいきません。
遺贈を受けるかどうかは自由です。
つまり、遺贈についても相続放棄と同様に放棄するという選択肢が与えられています。
【遺贈の放棄】
遺贈放棄の方法は特定遺贈と包括遺贈で異なります。
放棄の方法や方式が違います。別々に考えなければいけません。
■特定遺贈の放棄
特定遺贈の場合、その承認や放棄の方式について縛りがありません。
法令上の規定が存在しないのです。
受遺者は口頭や書面を問わず自由に放棄することができます。
相続放棄のように熟慮期間の定めもありません。
相続放棄のように家庭裁判所に申述をする必要もありません。
いつでも、どのような方式でも自由に放棄することができます。
しかし、受遺者がいつまでも放棄をするかどうか態度を明らかにしないと、相続人等の利害関係人の立場が不安定になり、法的安定が図れません。
利害関係人が不利益を受ける可能性すら考えられます。
そこで、相続人等の利害関係者は受遺者に対し特定遺贈を承認するか放棄するか態度をはっきりするように確認の催告をすることができます。
受遺者が定められた期間内に回答をしないときは承認したものとみなされます。
◆包括遺贈の放棄
包括遺贈の場合、特定遺贈とは異なり方式や期限を守り意思表示をしなければ、放棄の効力は生じません。
包括受遺者は、相続人と同じく相続財産について大きな利害関係を持つため何の制限もなく自由に放棄を認めるわけにはいきません。
そこで、包括遺贈の放棄についても相続放棄と同様の手順を踏まなければ効力が生じないものとしました。
受遺者は、自己のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に放棄の意思表をしなければなりません。
そして、その意思表示は家庭裁判所に対し行わなければ効力がありません。
遺言者の相続人や相続債権者に対し、放棄の意思を伝えても法的な効果は一切ありません。
つまりは、遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述しなければ遺贈を断ることはできません。
まとめ
■特定遺贈の放棄
相続放棄と違い、自由にいつでも放棄することができます。◆包括遺贈の放棄
相続放棄と同様に、3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述が必要です。